
![]()
天河大弁財天社
・・・HOMEに返る
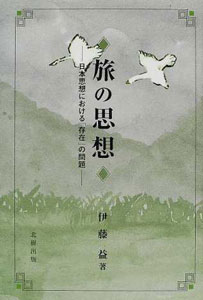
旅の思想
この道や 行く人なしに 秋の暮(芭蕉)茫漠と広がる原野に一筋の道が通っている。
・・・前ページに返る・・・HOMEに返る
古書肆 獺祭書房
(ダッサイショボウ)
獺(かわうそ)は、捕獲した魚を食べる前に岸辺に並べ置く習性を持つ。その様子になぞらえ、古来中国では詩作する人が机の周りに参考書籍を広げ散らすことを獺祭(だっさい)という。晩唐の詩人李商隠は、自らを獺祭魚と号し、広く故事を援用しつつ錯綜した時代の事蹟えを詩に定着した。明治の俳人正岡子規の庵には、獺祭書屋の名が付けられた。子規は、後半生を病に臥した畳の上で、幾多の魚を猟渉しては創作に没頭したことだろう。さて、現代の獺祭の徒、書物の山を前に好奇心旺盛なあなたを当店は応援します。
『七人の役小角』
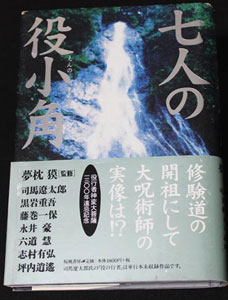
役小角(えんのおづの)は
大和国葛城上郡茅原(現在の御所市茅原)の生まれで、
修験道の祖と言われ、
役行者(えんのぎょうじゃ)とも呼ばれます。
後に朝廷から「神変大菩薩」の号を贈られています。
・・・HOMEに返る
『紀州・木の国根の国物語』
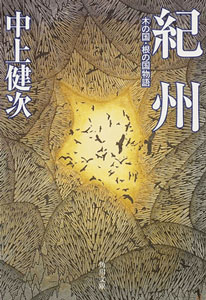
新宮生まれの作家、中上健次。 彼が自らの生まれ故郷の紀州を、半年以上掛けて聞き取り歩いたルポルタージュである。 新宮に始まり、東は松阪、西は和歌山市。紀ノ川を上って吉野も御坊も訪ね、十津川も行く。 地域に残る風俗風習を探し歩いた先人といえば柳田國男や宮本常一がいて、故事や事跡を訪ね歩いた達人に司馬遼太郎がいるが、中上の歩く場所は違う。 その取材対象の基準は、作者の言葉で言うところの「差別と被差別の回路」だ。 あまりにも、この本の世界は、深く、重く、湿って、粘って、暗かった。 どんよりとした、冷夏の真昼のうす曇の空のように。 光が差し込んでこない、そんな空は、中上の人生のように思えた。
・・・前ページに返る・・・HOMEに返る
サラスヴァティー(サラスヴァティー、サンスクリット:सरस्वती)

芸術、学問などの知を司るヒンドゥー教の女神である。
日本では七福神の一柱、弁才天(弁財天)として親しまれており、仏教伝来時に『金光明経』を通じて中国から伝えられた。
【容姿】
肌は真っ白く透き通り、額は三日月を付け[1]、4本の腕を持ち、2本の腕には、数珠とヴェーダ、もう1組の腕にヴィーナと呼ばれる琵琶に似た弦楽器を持ち、白鳥またはクジャクの上、あるいは蓮華の上に座る姿として描かれる。白鳥・クジャクはサラスヴァティーの乗り物である。
【神性】
サラスヴァティーは水辺に描かれる。サンスクリットでサラスヴァティーとは水(湖)を持つものの意であり、水と豊穣の女神であるともされている。インドの最も古い聖典『リグ・ヴェーダ』において、初めは聖なる川、サラスヴァティー川(その実体については諸説ある)の化身であった。流れる川が転じて、流れるもの全て(言葉・弁舌や知識、音楽など)の女神となった。言葉の神、ヴァーチと同一視され、サンスクリットとそれを書き記すためのデーヴァナーガリー文字を創造したとされる。後には、韻律・讃歌の女神、ガーヤトリーと同一視されることになった。
【神話】
ヒンドゥー教の創造の神ブラフマーの妻(配偶神)である。そもそもはブラフマーが自らの体からサラスヴァティーを造り出したが、そのあまりの美しさのため妻に娶ろうとした。逃れるサラスヴァティーを常に見ようとしたブラフマーは自らの前後左右の四方に顔を作りだした。さらに、その上に5つ目の顔(後にシヴァに切り落とされる)ができた時、その求婚から逃れられないと観念したサラスヴァティーは、ブラフマーと結婚し、その間に人類の始祖マヌが誕生した。また、元々はヴィシュヌの妻であり、後にブラフマーの妻になったという異説もある。
※wikipediaより
・・・前ページに返る
・・・HOMEに返る
辯才天
.jpg) |
| 「秦の始皇帝の侍臣,徐福着岸の趾」 |
 |
 |
「サラスヴァティー」の漢訳は「」であるが、既述の理由により日本ではのちに「辨財天」とも書かれるようになった。「辯」と「辨」とは音は同じであるが異なる意味を持つ漢字であり、意味の上では「辯才(言語の才能)」を「辨財(財産をおさめる、財産をつぐなう)」で代用することはできない。[1]。その一方、琵琶湖竹生島やその他各地には「辨才天」の名称も存在する。戦後、当用漢字の制定により「辯」と「辨」は共に「弁」で代用することになったので、現在は「弁才天」または「弁財天」と書くのが一般的である。
像容
弁才天立像(8臂像)京都府・浄瑠璃寺伝来(鎌倉時代 吉祥天像厨子絵)
原語の「サラスヴァティー」はインドの聖なる河の名である。サラスヴァティーには様々な異名と性質があり、弁才天も音楽神、福徳神、学芸神、戦勝神など幅広い性格をもつ。像容は8臂像と2臂像の2つに大別される。
8臂像は『金光明最勝王経』「大弁才天女品(ほん)」の所説によるもので、8本の手には、弓、矢、刀、矛(ほこ)、斧、長杵、鉄輪、羂索(けんさく・投げ縄)を持つと説かれる。その全てが武器に類するものである。同経典では弁才・知恵の神としての性格が多く説かれているが、その像容は鎮護国家の戦神としての姿が強調されている。
一方、2臂像は琵琶を抱え、バチを持って奏する音楽神の形をとっている。密教で用いる両界曼荼羅のうちの胎蔵曼荼羅中にその姿が見え、『大日経』では、妙音天、美音天と呼ばれる。元のサラスヴァティーにより近い姿である。ただし、胎蔵曼荼羅中に見える2臂像は、後世日本で広く信仰された天女形ではなく、菩薩形の像である。
日本における信仰と造像
弁才天坐像(妙音天)岩手県盛岡市・松園寺 弁才天坐像(宇賀弁才天)
滋賀県 竹生島・宝厳寺(1565年 浅井久政奉納) 弁才天坐像(個人蔵、鎌倉時代)
造像
日本での弁才天信仰は既に奈良時代に始まっており、東大寺法華堂(三月堂)安置の8臂の立像(塑像)は、破損甚大ながら、日本最古の尊像として貴重である。その後、平安時代には弁才天の作例はほとんど知られず、鎌倉時代の作例もごく少数である。
京都市・白雲神社の弁才天像(2臂の坐像)は、胎蔵曼荼羅に見えるのと同じく菩薩形で、琵琶を演奏する形の珍しい像である。この像は琵琶の名手として知られた太政大臣・藤原師長が信仰していた像と言われ、様式的にも鎌倉時代初期のもので、日本における2臂弁才天の最古例と見なされている。同時代の作例としては他に大阪府・高貴寺像(2臂坐像)や、文永3年(1266年)の銘がある鎌倉市・鶴岡八幡宮像(2臂坐像)が知られる。近世以降の作例は、8臂の坐像、2臂の琵琶弾奏像共に多く見られる。
松葉の効用
松葉( マツ科:常緑高木:樹高10~30メートル:花期 3~4月 )
名前の由来は、マツは、古くから神聖な木として考えられていたようです。神がマツの木に天から降りることを、待つ(マツ)という説があります。また、マツの葉が二股に分れている様子から、股(マタ)から転訛(てんか)して、マツという名がついたという説もあります。
1、薬効
松葉には、クロロフィル、ビタミンA・C・K、鉄、リン、食物繊維、松ヤニ、シネオールという精油成分などが含まれています。
効能としては、血管を強くして、血液の流れをよくし、動脈硬化、心筋梗塞、高血圧、ボケ、脳卒中を予防します。頭部の血行も促進しますから,頭皮と毛髪に栄養が行き渡ることにより、抜け毛を防ぎ、育毛を促進します。関節痛・湿疹・かゆみ、打撲、むくみ、低血圧症、冷え性、不眠症、食欲不振、膀胱炎、動脈硬化症、糖尿病、リューマチなどにも効果があると言われています。
またタバコの有害物質でもあるニコチンを外へ排出するはたらきがあるので、タバコを吸う人に有効です。
2、マツの有効成分
| 葉緑素クロロフィル | 増血作用、血液浄化、血液中の不飽和脂肪酸溶解 |
| ・テルペン精油(ピネン、ジペンテン、リモネン含有成分) | 血液中のコレステロール除去し血液をサラサラにしてボケ・脳卒中・動脈硬化を抑制 |
| ・ビタミンA・C、ビタミンK、鉄分、酵素 | 血液の凝固、骨へのカルシウム沈着・老化を抑制し出血を防ぐ |
3、用い方
| 塗布 | 肩こり、筋肉痛、あかぎれ、打撲傷に松脂を患部に塗布します。 |
| 松脂の粉末 | 低血圧症、冷え性、不眠症、食欲不振、去痰、膀胱炎、動脈硬化症、糖尿病、リューマチ、神経痛、健胃、疲労回復、心臓病などに松脂の粉末を酒にいれて飲用します。 |
| 飲用 | 去痰には、2グラムの松脂と焼酎0.01リットルで溶かして水0.2リットルと砂糖3グラムを加えて飲用します。 |
| お茶 | お茶としての利用法:松(赤松が一番いい)の新葉青々としたものを採取します。刻んで天日干してカラカラにします。ミキサーで粉末にして保存します。5グラムに水0.5リットルを30分細火で煮出して飲用するか、お茶のようにお湯を注いで飲用します。 |
| 焼酎 | 松葉酒は松葉(生松葉)を適量と焼酎を加えて1~3ヶ月冷暗所に保存したあと、飲用します。ハチミツや黒砂糖を入れると飲みやすくなります。 |
| 煎じて | 生のマツ葉を煎じて、うがいをすると虫歯や口内炎治療の効果もあるとされます。マツには、松脂成分テルペン油に鎮痛作用があるとされています。 |
| 噛む | 生の青いマツ葉を採取して良く洗い、半分くらいに折って、折った方から口に入れて、軽く噛みます。噛んだ後には吐き捨てます。それで、精神集中や歯の病気の予防になるとされます。これは、簡単ですから、一度試してみてください。 |
| 発酵酒 | 松葉の発酵酒は、新鮮な生の松葉を良く洗い、1升ビンに半分量程度を入れます。水を8分目くらい入れて、布のふたをします。晴れた日に太陽にあてて、曇ったら取り込みます。発酵して炭酸ガスが沸いてきますので。ときどきビンを注意して見ます。炭酸ガスが沸かなくなったら、約1週間程度で出来あがりです。コップ1杯を朝晩飲用。5日ほどで飲みあげるようにします。カビには十分注意してください。 |
| ジュース | 松葉ジュースは、青く新鮮な松葉10グラム程度の根元のさやを取り除いて水洗いします。水0.2リットルと皮をむいたレモン半分を加え、ジューサーに30秒程度かけます。ハチミツで甘味をつけてそのまま飲みます。バナナ、リンゴ、アシタバ、パセリなどを入れてブレンドしたジュースも味わいがあります。 |
| サイダー | 松葉サイダーは、まず、一升瓶に砂糖100g入れ、刻んだ松葉を入れます。量は、瓶の中にどんどん入りにくくなるまで入れます。その後はイースト菌を入れ、水を8分目まで入れ、日当たりのよい、日だまりのようなところにおいて発酵を促進してください。あとはじっくり待つだけです。途中、布でこして、さらに発酵させる方法もありますが、松葉を除かず、飲みきるまで入れておくほうが効果がよいようです。 |
《松葉エキスの利用法》
健康食品として、松葉エキスを飲みやすい錠剤や丸薬の形にしたものや、松葉エキス入りのガム、キャンディーなどがあります。生の若葉を用いるときは、細かく刻んですり鉢に入れてつぶし、弱火にかけて浸出してくる精油分を搾り取ります。ハチミツを加えると飲みやすくなります。ごく新鮮なものなら、生のまま松葉汁を飲み干す方法もあります。副作用や有害成分は特にありません。
松葉は不老長寿の妙薬として仙人が用いたといわれ、昔から薬効のある素材として民間療法に広く使われてきました。中風に効くとされて、予防や治療に用いられました。黒松や赤松の葉をすりつぶして煮ると、シネオールという精油成分が出てきますが、これを搾り摂ったものを松葉エキスといい、健康に利用さえれてきましたが、最近では摂取しやすい形の松葉エキス健康食品を用いるのが一般的になっています。
《松湯のレシピ》
松の葉の煮汁を加えたお風呂が、松湯です。松の葉には、皮膚を刺激して血行を促進する精油成分が含まれているので、松湯に入ると身体の隅々まで血液が循環し、その結果、神経痛やリウマチ、肩こり、腰痛が軽減されます。また、松の芳香成分には、疲労感を和らげてくれる作用があります。
松葉はその都度、生のまま使用します。家庭の浴槽なら1回200~250gの松葉を、まずは樹脂成分が残らないようにぬるま湯でよく洗います。その後、鍋に入れ、水から火にかけて15~20分間煮出した煮汁のみを、布でこして浴槽に加えます。雰囲気を楽しむなら、生の松葉を浮かべてみてもいいでしょう。
鄷都に地獄がある
…初期の漢訳仏典で,地獄の語の代りに〈泰山〉の語が用いられるのは,そうした中国の伝承を利用したものであり,逆に泰山にある死者の世界も仏教の地獄に似たものとして描かれることにもなる。泰山とならぶもう一つの中国的な死者の世界,羅鄷都(らほうと)(鄷都)の詳しいようすが述べられるようになるのは六朝中期ごろからで,《真誥(しんこう)》に見えるそれは中国から遠く隔たった北方の地にあるのであるが,やがて四川省の鄷都に地獄があるのだとされるようになり,近世,その地では地獄にまつわる呪術的信仰と民間伝承とが発達した。道教内部にあっても,仏教の影響を受け,また民間伝承も取りこんで,唐代にはすでに八地獄,二十四地獄,三十二地獄といった地獄の組織化がなされている。
天河の本尊の弁 天像

弘法大師は中国で学んだ知識を活かして各地の土木工事の指揮を取ったり、 また庶民教育のための学校を設立するなど、非常に精力的な活動をしていま す。また、彼は書道でも非凡な才能を発揮、後に彼は嵯峨天皇・橘逸勢と共 に三筆と呼ばれることになりました。また絵画や彫刻の才能もあったという ことで、彼は宗教家としてのみでなく、社会事業家・芸術家としても精力的 に活動をしたのです。
※上写真はこれと思うのですが参考。非凡。
空海 年譜
| 和暦 | 西暦 | 日付 | 年齢 | 事柄 |
|---|---|---|---|---|
| 774年 | 香川県善通寺市 誕生 真魚 | |||
| 延暦11年 | 792年 | 18歳 | 長岡京の大学寮に入り、明経道を専攻する。 | |
| 延暦17年 | 798年 | 24歳 | 聾瞽指帰を著した。 | |
| 延暦23年 | 804年 | 31歳 | 東大寺戒壇院で得度受戒した。 | |
| 延暦23年 | 804年 | 12月23日 | 31歳 | 第16次遣唐使留学僧として長安に入った。 |
| 延暦24年 | 805年 | 5月 | 32歳 | 密教の第七祖・青龍寺の恵果和尚に師事。 |
| 延暦24年 | 805年 | 8月10日 | 32歳 | 伝法阿闍梨位の灌頂を受け、遍照金剛の灌頂名を与えられた。 |
| 大同元年 | 806年 | 10月 | 33歳 | 20年間の予定を2年間で帰国したため、帰京の許可を得るまで大宰府の観世音寺に滞在することになった。 |
| 弘仁7年 | 816年 | 7月8日 | 43歳 | 朝廷より高野山を賜る。 |
| 弘仁12年 | 821年 | 48歳 | 満濃池の改修を指揮した。 | |
| 弘仁13年 | 822年 | 49歳 | 太政官符により東大寺に灌頂道場真言院を建立した。平城上皇に潅頂を授けた。 | |
| 弘仁14年 | 823年 | 正月 | 50歳 | 太政官符により東寺を賜り、真言密教の道場にした。 |
| 天長5年 | 828年 | 12月15日 | 55歳 | 京に私立の教育施設「綜芸種智院」を開設した。 |
| 天長9年 | 832年 | 8月22日 | 59歳 | 高野山において最初の万燈万華会が修された。 |
| 承和2年 | 835年 | 3月21日 | 61歳 | 入定した。 |
| 延喜21年 | 921年 | 10月27日 | 東寺長者観賢の奏上により、醍醐天皇から「弘法大師」の諡号が贈られた。 |
※wikipediaより
NPO法人東京自由大学 セミナーのご案内
| 5月のセミナー | 身体と霊性 第2回:「日本治療家・霊術家列伝」 津村喬×鳥飼美和子(聞き手) |
|
| 日程 | 2017年5月20日(土) | |
| 時間 | 14:00~16:30 | |
| 受講料 | 一般 | 2500円 |
| 会員 | 2000円 | |
| 学生 | 1000円 | |
| 学生会員 | 500円 | |
| 会場 | あおぞら銀行オアシスルーム | |
| 住所 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5丁目28−1 | |
| ◆振込み先 | 振込先ページッジャンプし先宛へ | |
| 今回のセミナーは、会場の都合により事前振込が必要です | ||
◆お問い合わせのメールは kikoubunka@yahoo.co.jp か
◆FAX 075-777-7719 でどうぞ。


